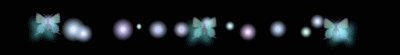深淵
あいつのあんな姿を見たのは初めてだった。
何時も気の抜ける笑顔で遠慮もなしに近付いてくる城戸が、項垂れて蹲っている。
優衣に、城戸がゾルダを殺したと聞いた。
ライダ−同士の戦いを止めさせると、モンスタ−を倒す為だけに戦うと言った城戸が、初めて仲間を手にかけたのだ。
慰めるつもりなど毛頭なかったが、その姿を見た瞬間言葉が出てこなかった。
無言で近寄る俺を見上げた、城戸の瞳に映った絶望に息を呑んだ。
縋るような視線を向けたのは一瞬で、また直ぐに顔を伏せる。
――― 他人を手にかけるというのは、こういう事か・・・。
「 奴も、ライダ−になった時から死は覚悟の上だっただろう」
漸くそれだけを口にしたが、城戸の口から出たのは意外な言葉だった。
「 あの北岡さんが泣いたんだ 」
もうどうしたらいいか解からない、と続ける城戸の顔を呆然と見詰めた。
ゾルダは、北岡だ。
どうやら城戸はかれの秘書がゾルダの正体だと思い込んでいるらしい。
馴れ合いは嫌いだった。ゾルダの正体を城戸に教えなかったのはそんな理由だった。
だが、こんな事になるのなら教えていた方が良かったのか。
「 もういいよ 」
そう言って背を向けた城戸から視線を外し、俺は唇を噛んだ。
この男を放って置けない自分に苛立たしさを感じる。
だが、北岡に傷つけられる城戸をこれ以上見ている事も出来なかった。
不本意ながら俺は北岡を罠にかけ、その正体を城戸に教えた。
しかし、ゾルダの正体を知り、彼の秘書である由良吾郎の無事を知った城戸の口から出たのは怒りの言葉ではなかった。
「 生きてたんだな、良かった・・・ 」
心から安堵の溜息を漏らす城戸を見つめる北岡の横顔を見ながら、彼もまた自分と同じ様に戸惑っている事が解かった。また、城戸の笑顔に救われている事も・・・。
俺が ――― そして多分北岡も、城戸を認めた瞬間だった。
同じ部屋の、城戸のベッドから寝息が聞こえる。
カ−テンを開けて覗くと、彼はぐっすりと眠り込んでいた。
何時だったか、同じ様に寝ている城戸を見下ろした。今日と同じ、静かな晩だった。
無実の罪で城戸が警察に拘留されていた時。同じ部屋で過ごしたのは数日だというのに、何故か静かな部屋に落ち着かず、眠れなかった。
・・・ その後隣に城戸の気配が戻った夜だ。
俺はぼんやりとその時の事を思い出していた。
鼓動を確かめるように彼の首筋を指で辿った。寝息を確かめるように、薄く開いた唇にも指を這わせ、それから、顔を寄せた事を。
触れた途端寝返りを打った城戸から身体を離して自分の行動に驚いた。
現在は、何となくその行動の意味が理解できた。
しかし、彼の存在を必要としている自分をどうしても認める事はできない。
相反する想いを抱えて、ただ、眠る城戸を見下ろしていた。
「 ん ・・・ 」
ごろりと身体の向きを変えて、再び寝息を立てる城戸の晒された項に目が吸い寄せられる。
その時、不意にあの夜の感覚が手に、そして唇に蘇って来た。
熱い固まりを呑み込んだように、身体がかっと燃え立つ感覚を覚える。
開かない瞼を無理矢理開けて、真っ直ぐな視線を見たいと思った。
その瞳が傷つき、絶望を浮かべる様をもう一度見てみたいという欲求に駆られる。
恐らくこの男は、誰にでも簡単に傷をつけさせる事を許すのだろう。
そして、誰にでも癒されるのだ。一つの物に執着がなく、他人に同様に心を開くというのはつまり、そういう事だ。
これからも現れるであろうライダ−達に対しても戦いを止めさせようとする。
その度に傷つき、死に近付く。
危険に真っ正面から飛び込む城戸は、多分自分よりも死に近い生き方をしているだろう。
そう思うと止められなかった。
他の誰かの手に落ちるくらいなら、この手で息を止めてやりたいとさえ思った。
ベッドに体重をかけると、ぎしりと嫌な音がした。
「 ん−・・・ ? 」
その音に城戸の瞼がぴくりと動き、睫毛が揺れる。
城戸が完全に目を開ける前に彼の上に馬乗りになった。
「 うわっ!?誰だ!? 」
驚いて身を起こそうとする城戸の肩を無理矢理ベッドに縫い付ける。
「 何だ、蓮か? 」
暗い室内を照らすのは微かなライトの明かりだけで、城戸は目を細めて俺を確認したようだ。
「 何してんだよ?・・・ あ、まさか今から戦おう、とか言い出すんじゃないだろうな?」
半分寝惚けたまま、引き攣った笑顔を向けるが、その表情には疑いの色などまるでない。
これから俺がしようとしている事を、こいつはどう受け入れるのだろうか。
「 ・・・ 離せよ 」
身動ぎして、固定されたままの肩を動かそうとするが、俺の手が外れないのに眉を寄せる。
わざとゆっくりとした動きでその唇を塞いだ。
途端、暴れ出す身体を体重をかけて押さえつける。
触れるだけだった以前とは違い、今度はその唇を割って舌を絡めた。
城戸は簡単に侵入を許した。或いは、慣れていないのかもしれない。
押し返そうと力を込める手は次第に力を失くし、足だけがシ−ツを空しく蹴っていた。
頭を左右に振って漸く口付けから逃れると、城戸は空気を求めるように何度も呼吸を繰り返し、俺を睨み付けた。
「 何すんだよ!? 」
「 ・・・ 酔ってるんだ 」
薄く笑みを乗せると、城戸は唖然とした表情で見上げてきた。
もう一度唇を被せ、パジャマの裾から手を滑り込ませる。
滑らかな肌がぴくりと反応した。
「 ・・・ やめ、ろよ ・・・ 」
再び城戸の手に力が戻り、覆い被さる身体を押し除けようとする。
「 騒ぐと優衣が起きる 」
その言葉に城戸の動きがぴたりと止まった。
しかし、胸を滑る手を下肢に伸ばしてその中心を弄ると城戸は慌てて飛び起きようとした。
「 ばっ・・・、やめろって・・・ ! 」
「 往生際が悪いな 」
浮いた城戸の背中を片手で乱暴に押し戻し、もう一方の手に力を込める。
痙攣したように、その背がびくりと跳ねた。
強弱をつけて愛撫を繰り返すと、次第に形を作りはじめる彼を感じた。
顔を覗き込み、固く瞼を閉じたまま唇を噛み締めている城戸に口付けた。
その瞬間、彼の目尻から涙が零れ、頬を伝う。
「 何でだよ ・・・ 。自分が何してるか、解かってんのかよ・・・ 」
――― よく、解っている・・・ 。
口には出さなかった。
代わりに上下に動かす手の動きを早め、彼を追い詰めた。
肩にかけられた指先に力がこもり、白く変色する。
「 はっ・・・、あ・・・ っ 」
耐え切れず漏らす息が荒いものに変り、城戸はあっけなく欲望を吐き出した。
彼の息が整うのを待ち、薄っすらと開けた目の前に彼の吐き出した欲望を見せ付けてやると、その白い頬がかっと紅潮した。
すっかり力を無くした足を持ち上げ、今度は後ろに指を這わせる。
「 やめ ・・・ 、」
拒絶の言葉は途中で途切れた。
与えられる感覚に、戸惑うように見開かれる瞳。
潤滑液のお陰ですんなりと指を受け入れた城戸は、不快そうに眉を顰めた。
「 動くな 」
指を中に収めたまま、片手で器用に自分の衣服を取り去る俺を、城戸は身動き一つせず見上げている。
「 蓮、やめろよ・・・ 、・・・ 嫌だ ・・・」
身体を固くしたまま、脅えの混じった視線を向ける彼に、自分でも驚くほど残虐な欲望が湧き上がるのを感じた。
何も言わず指を引き抜くと、一気に彼の中に押し入る。
「 う・・・、あぁ・・・っ 」
苦痛に顔を歪め、尚も嫌だと首を横に振る城戸の顎を捕らえ、唇を貪った。
お互いに何も考えられなくなる程、思う様揺さ振り、快楽の波に身を委ねてゆく。
「 蓮、・・・ 蓮 」
制止の響きが交じる呼びかけが、次第に甘く掠れてくるのを頭の隅で聞いていた。
翌朝、仕事へ行くぎりぎりの時間に目を覚ました城戸が、鈍い動きで階段を降りてきた。
既に店の開店準備を始めている三人に視線もくれず、一言も口を開かないまま、彼は店のドアを開けて出て行こうとする。俺はその後を追って、原付に跨りヘルメットを被ろうとする城戸を呼び止めた。
「 何も、言わないのか? 」
俯いて視線を合わせる事を拒む城戸を冷たく見据えた。
「 ・・・ 何か、言って欲しいのかよ 」
昨夜の事は充分に彼を傷付けたらしい。彼の態度は予想通りだった。
「 帰ったら、全部忘れてやるから。酔ってるからって二度とあんな事すんなよ」
それもやはり、予想通りの言葉だった。城戸は何もなかった事にしてしまいたいのだ。
それは許さない。
「 どうして忘れるんだ?・・・ 終わりなどない。お前が俺の近くにいる限り」
城戸は顔を上げると俺を見つめた。
「 じゃあ、離れるよ 」
あっさりと背を向ける城戸に唖然とし、同時に腹が立った。
「 逃げるのか? 」
「 逃げる。・・・ 戦う理由なんて欲しくないから」
―――― それは ・・・ 。
城戸の肩に手をかけ、振り向かせる。
「 それは、どういう意味だ? 」
戦う理由。今の状況では、自分に対する憎しみであるとしか考えられなかった。
では、殺したいほど俺を憎んでいる、というのか・・・。
笑い出したい衝動に駆られる。それこそ、望んだ結末だった。
これで迷うことなくこいつを切り捨てる事が出来るのだ。戦いに躊躇う事もなくなる。
城戸は小さく息を吐くと、ぽつり、と言葉を発した。
「 大切な物を選ぶのは昔から苦手なんだ。一つだけに決められない」
「 ・・・・・ 」
城戸が何を言おうとしているか解らなかった。
「 それを手にとってしまったら、他のものを捨てなくちゃならなくなる。大切なものを守る為に、戦う事になる」
一瞬、自分の事を言われているのかと思った。
城戸が絵里の存在を知る筈はないのに。
「 怖いから、逃げるんだ 」
「 ――――― 」
城戸の弱さを垣間見た気がした。
全てを受け入れて真っ直ぐな視線を持ち続ける事が出来るのは、固執するものがないからだ。
守りたいもの。その存在は人を強くもするが、また、弱くもする。
城戸の強さの、正体を知った。
「 ・・・ 能天気じゃ、なかったのか 」
俺の言葉に城戸は笑った。何時もの笑顔で。
「 じゃ、俺遅刻するから 」
そう言ってエンジンをかける城戸に、声をかけた。
「 忘れろ 」
一言。
それで本当に全てが許される筈も、忘れられる筈もなかったが、これ以上は何も変わらないと悟った。躊躇いも苛立ちも消える事はない。
自分が何をしたかったのか、それすら解からなくなる。
だが、振り向いた城戸の瞳に浮かんだのは怒りでも安堵でもなかった。
昨日よりも更に傷付いた目をしていた。
「 ・・・ ああ 」
頷いて、ヘルメットを被りアクセルを回すと、エンジン音と共にその後ろ姿が小さくなる。
半ば呆然と彼の背中を見送った。
“ 忘れたい ”そう言ったのは城戸自身だった筈だ。
全てをなかった事にして、日常に戻るのだと・・・ 。
では、城戸の“ 大切なもの ”とは何だ?
自分が揺らぐ程の、逃げ出す事を選ぶ程の、その存在。
「 ・・・ まさか ・・・ 」
ふと浮かんだ考えを、頭を振って追い出す。
そんな筈はない。
だが、先程の辛そうに歪んだ城戸の表情が頭から離れなかった。
自分の、そして彼の暗い淵を覗いた気がした。
終
終わっときます〜。何を書きたいんだか途中でわかんなくなっちゃったよ〜。
力尽き・・・、ばた・・・。