鏡影と共に…
それは、確かに恋ではなかった。
理想的で擬似的な家庭生活を押し付けられて過ごした孤児院を出た後、全寮制の学校へ入った。他に行くべき所も、行きたい所もなかったから。
物心ついてからは、笑った記憶がない。
遠巻きに自分を見ている他人の中に、特に関わってくる者もいなかった。
その中で彼女だけが僕の目の前に立ち、真っ直ぐな視線を向けた唯一の存在。
図書室へと続く長い渡り廊下でいきなり声を掛けられた。
「 はじめまして…。猪悟能ね? 」
「・・・ 」
あからさまに迷惑な表情をする僕に、彼女は平然と、
「 全然笑わないのね。友達、いないんじゃないの?」
「 僕が笑わない事があなたに何か関係あるんですか?」
正直、こうして関わってくる女性なら何人か居た。
だが、それに関心を引かれた事も、魅力を感じた事も皆無だ。
自分でも何処か感情が欠落しているとしか思えなかったが、別に生きていくのに支障がある訳ではなかったし、必要のないものだった。
「 …私と、一緒 」
ぽつり、と彼女が漏らした言葉に視線もくれずその場を去ろうとする僕に、その白く細い手が伸ばされた。
「 こっち見て 」
「 …いい加減にして下さい。暇じゃないんです
」
無下に振り払おうとした僕の腕を、意外に力強い手が引き止めた。
「 私には分かった。だからあなたにも分かる筈なの
」
静かだが、熱の篭った声。
渾身の力で腕を握り締める。
その強さに、漸く目線を彼女の瞳に合わせてみた。
こちらを見上げる碧の、瞳。
「 偶然じゃないわ。同じなのよ 」
「 ―――――・・・ 」
確かに似ていた。
自分の、それに。
「 聞いたことあるでしょう?生き別れの姉弟の事
」
「 知りません 」
これが本当なら、陳腐な三流小説の様だ。
生き別れの双子の姉弟が再会なんて。
涙を流して喜び合えば彼女は満足なのか?そんな真似はごめんだ。
今更家族ができたって意味がない。
欠落した感情は埋まる事はないのだから。
「 用はそれだけですか?…でしたら失礼します
」
自分でも驚くほど、心が急激に冷えていくのを感じていた。
そっと手を放した彼女に冷たい一瞥を投げかけて、再び図書室へと向かった。
適当に選んだ本を抱えて、広い図書室の一番奥の席に落ち着いた。
先程の事を頭から追い出そうと本に没頭していたが、周りのこちらに向けられる視線に気付いて顔を上げた。
自分の姉と称する先刻別れたばかりの彼女が、真っ直ぐに僕の座る席に向かっていた。
それに対して何故周りが注目するのかと、訝しむ。
「 珍しいんでしょう、何時も独りで居る私達が一緒に居るから
」
それにあなた目立つし、と付け加えた彼女の方が視線を集めている気がするのだが、特に何も言わなかった。
こうして向かい合って座っていると、自分達が本当によく似ている事が分かった。
他人から見ても分かるのだろうか…。
「 場所を変えましょう 」
これ以上好奇の視線に晒されるのが嫌で、僕は彼女を促した。
校内では落ち着いて話しも出来ないので、寮の近くの小さな中庭まで二人で歩いた。
風がそよぐ暖かな昼下がり。
日の光を受けて輝く木々の緑にさえ、心が動く事はなかった。
彼女も同様に、風景など少しも見てはいなかった。
「 …で?家族の再会を喜び合いますか?言っときますけど、僕は孤児院に居た時の記憶しかありませんし、財産も何もありませんよ
」
「 わかってる。私も一緒だから 」
顔を上げた彼女は、静かに話し出した。
「 一目見て分かったの。あなたと私は同じだって。…私も笑えないのよ
」
訴えるように向けられる瞳にも、自分には応える術がない。
「 だから、傷を舐め合って慰め合って生きていこう、とでも?」
「 それでもいいわ…。ただ、私は自分を愛せない。でも、あなたなら、愛せる
」
その言葉に弾かれたように彼女を見つめた。
“自分を愛する事ができない”それはおそらく、二人の欠落した部分。
鏡に映った半身を愛する。
そうする事で埋める、というのか。
「 あなたが笑ってくれたら、私も笑える気がするの
」
「 ・・・・・ 」
ふと、それでもいいだろう、という考えが浮かんだ。
彼女の言うように、自分の半身である彼女を守って生きてみようか…。
特に意味のある人生ではない筈だから、先の事など何も考えないで…。
僕の心を読んだように、彼女がにっこりと微笑んだ。
「 悟能 」
軽く背伸びをした彼女の顔が近付いて、僕にキスをした。
「 …姉弟のキスですか?」
「 違うわ。私達は全てを埋め合うの。…今までの分、全て…
」
「 名前を、教えて 」
「 花喃 」
その時初めて、彼女がとても綺麗な事に気が付いた。
その後、僕たちは学校を辞め、誰も知らない場所へ移り二人で暮らし始めた。
必然のように、肌を重ねた。
白くて柔らかい、自分とは全く違う身体。
それを確かめるように手を這わせると、甘い吐息が花喃の小さな唇から漏れた。
「 悟能は…、初めて?」
「 試した事はある 」
何でもない事だと吐き捨てた言葉に、花喃はそう、と呟き、
「 私も… 」
小さく告白したが、嘘だという事は直ぐに分かった。
繋がった瞬間、悲鳴に似た声が上がり、白いシ−ツに紅い染みが広がった。
半分泣きながら、それでも必死に笑顔をつくって、
「 私達、双子で良かったね。…男と女で、良かった
」
そう繰り返す花喃の細い身体を抱きしめた。
もともと神の存在など信じていない僕たちに、怖いものなど何もなかった。
もし、僕の方が先に彼女を見付けていたら、きっと同じ様に彼女を求めていただろう。
他の誰も変わりになどできない。
異常な愛の形。
だからなのか、その終極も、歪んでいた。
僕たちはよく似ていたから。
誰にも邪魔されないように、努めて外では当たり障りの無い態度を心掛けた。
笑顔の作り方、相手を逆なでしない言葉遣いはここで身につけた。
敵さえ作らなければ、平穏に暮らせると思っていたから。
でもそれは嘘だったと突然に気付かされた。
自分達を守る為に花喃を妖怪に差し出した村人。
利己的なのは自分達だけじゃない。
皆、同じだ。
そう思うと、もう自分を止める事は出来なかった。
ほとんど無抵抗な村の人間と花喃を攫った妖怪を、怒りのままに、数える事も出来ないほど引き裂いた。
それが全て、無意味な行為だと気付く事もなく・・・。
―――― 花喃は、解っていたのだろうか。
僕が壊れていく事を。
解っていて、自ら僕の目の前で命を絶ったのだろうか。
救われる事など望んではいなかったのに。
今僕は、君のいない場所で生きている。
君の知らない場所で、君の知らない人と笑ってる現在の僕の事を、あの時君は解っていたの…?
君も今、笑っている…?
脳裏に刻み付いた死に顔は何も答えてはくれないけれど、僕は繰り返し問い掛ける。
失う事よりも消える事を選んだ自分の半身に
――――――。
それは、恋じゃなかった。
だけど、僕は確かに君を愛していたんだ…。
end
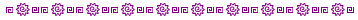
どうも花喃さんは暗いイメ−ジで見てしまいます。
八戎さんが本当に恋をするのは三蔵様にのみ!と信じて疑わない私の
願望の表れです!次こそ、表に三×八やろう!